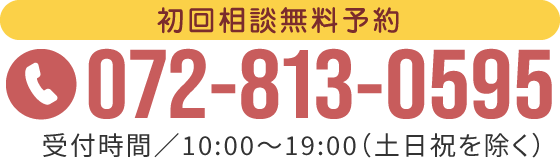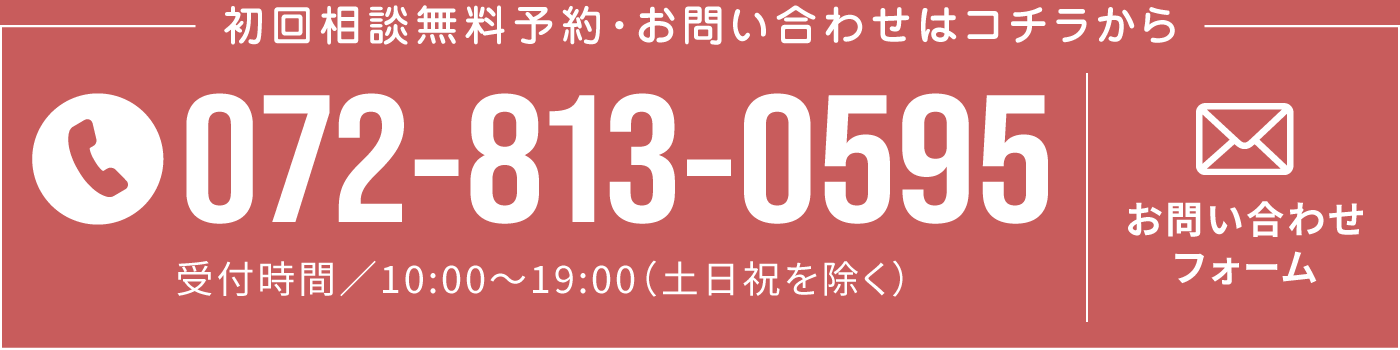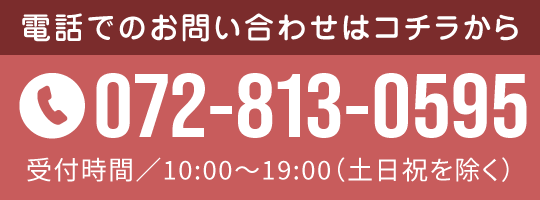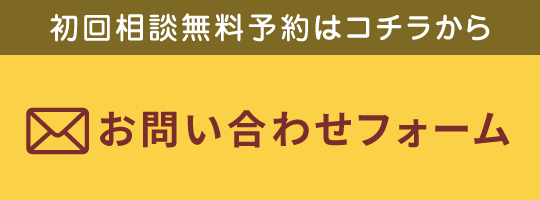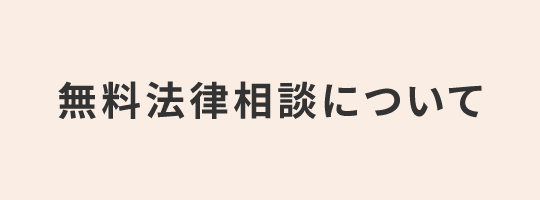このページの目次
📄 ご相談の背景
今回ご相談に来られたのは、70代の鈴木様(仮名)です。鈴木様は、ご自身の事業を長年支え、現在も同居して身の回りの世話をしてくれている長男の太郎さん(仮名)に、ご自身の財産である不動産の共有持分と預貯金2,000万円のすべてを相続させたい、と固い決意をお持ちでした。
鈴木様には、遠方に嫁いで家庭を築いている長女の花子さん(仮名)もいらっしゃいます。花子さんとは良好な関係を築いており、花子さん自身も「家や事業のことはお兄ちゃんが継ぐのが当たり前よ」と普段から話しているとのこと。そのため、鈴木様は「花子もきっと納得してくれるはずだ」とお考えでした。
しかし、ご友人の相続で揉めた話を聞いたことをきっかけに、本当にご自身の希望通りの遺言書を作成して、それだけで万事うまくいくのだろうかと、一抹の不安を覚えるようになりました。特に、法律で定められた相続人の最低限の取り分である「遺留分」という言葉を耳にし、このまま自分の想いだけで進めてしまって、太郎さんと花子さんの兄妹仲に亀裂が入るような事態にならないか、と心配になり、当事務所へご相談に来られました。
💬 ご質問と弁護士の回答
質問1:「『全財産を長男の太郎に相続させる』という内容の遺言書を作成することは、法的に可能なのでしょうか?」
回答:
はい、ご自身の財産を誰に、どのように相続させるかについては、遺言書によって自由に定めることが可能です。これを「遺言自由の原則」といいます。したがって、「全財産を長男の太郎さんに相続させる」という内容の遺言書を作成すること自体は、法的に全く問題なく、有効です。まずはこの点でご安心ください。ご自身の想いを形にするための第一歩として、遺言書は非常に強力な法的手段となります。
質問2:「では、その遺言書さえ作っておけば、将来、長女の花子から何か言われる可能性は一切ないと考えてよいのでしょうか?『遺留分』という制度が気になっています。」
回答:
鈴木様がご心配されている通り、注意すべき点がございます。遺言書が法的に有効であることと、他の相続人から何も主張されないこととは別の問題です。
お子様である長男の太郎さんと長女の花子さんには、それぞれ「遺留分(いりゅうぶん)」という、法律によって保障された最低限の遺産取得分があります。今回のケースでは、花子さんは法律で定められた相続分(法定相続分)のさらに半分(遺産の1/8)を遺留分として受け取る権利を持っています。
鈴木様が作成された遺言書の内容が、この花子さんの遺留分を侵害するものであった場合、花子さんは遺言によって全財産を受け取った太郎さんに対して、「遺留分侵害額請求」という形で、侵害された分に相当する金銭を支払うよう請求することができます。もちろん、花子さんがこの権利を行使するかどうかはご本人の意思次第ですが、相続が発生した際に、お金の話が絡むと、それまでの関係性が変わってしまう可能性は残念ながら否定できません。
質問3:「長男と長女の間で争いが起きないようにするためには、具体的にどのような対策をすれば良いのでしょうか?想いを伝える良い方法はありますか?」
回答:
将来の紛争を未然に防ぎ、鈴木様の想いを円満に実現するためには、いくつかの重要な対策があります。
一つは、遺留分について予め配慮した内容の遺言書を作成することです。例えば、預貯金の一部を花子さんが取得できるように指定するなど、遺留分を侵害しない、あるいはそれに近い財産を渡す形が考えられます。
そして、それ以上に重要になるのが、遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」を活用することです。付言事項には法的な拘束力はありませんが、「なぜ長男に全財産を相続させたいのか」という鈴木様の本当の想いや、長男・長女それぞれへの感謝の気持ちなどを、ご自身の言葉で書き記すことができます。
「事業を守り、最後まで生活を支えてくれた太郎に財産を託したい」「花子には生前こういう援助をしてきたし、何より幸せな家庭を築いてくれていることを誇りに思う」といったメッセージを残すことで、単なる財産の分配指示書ではない、「家族への最後の手紙」として、花子さんの心情に訴えかけ、遺留分侵害額請求という権利の行使を思いとどまらせる効果が期待できます。どのような文面にするか、どの程度の財産を配分すればご家族が納得しやすいかなど、専門的な知見を踏まえた作成が極めて重要になりますので、ぜひ弁護士にご相談いただきたい部分です。
📌 この事例のポイント整理
- 遺言書によって、特定の相続人に全財産を相続させるなど、財産の分け方を自由に定めることは原則として可能。
- ただし、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)には、遺言によっても奪われない最低限の取り分「遺留分」が保障されている。
- 遺留分を侵害する内容の遺言も無効ではないが、他の相続人から金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)されるリスクがある。
- 将来の紛争を防ぐためには、遺留分に配慮した遺産分割や、感謝や理由を伝える「付言事項」を遺言書に盛り込むことが非常に有効。
📣 弁護士からのアドバイス:想いを伝える「付言事項」が、円満相続の鍵です
遺言書は、単に財産をどう分けるかを指示するだけの事務的な書類ではありません。残される大切なご家族へ宛てた、「最後のメッセージ」としての役割も持っています。
特に、今回のご相談のように、特定の相続人へ多くの財産を遺したいとお考えの場合、なぜそのような内容の遺言を遺すのか、その「理由」と「想い」を伝えることが、法的な規定以上に重要になることが少なくありません。
「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が現実のものとなると、それまで表に出なかった感情や、配偶者など周囲の意見も絡み、予期せぬトラブルに発展してしまうケースは、残念ながら数多く見てきました。
法的に有効な遺言書を作成するのはもちろんのこと、ご自身の真意を「付言事項」という形でしっかりと記し、残されたご家族が円満に相続手続きを進められるよう、万全の準備をしておくこと。それが、ご自身の想いを実現し、ご家族を守るための最善の方法です。
🏢 遺言書作成のご相談は、大東法律事務所へ
遺言書の作成は、ご自身の人生の集大成であり、ご家族への想いを形にする大切な作業です。しかし、法律的な知識が不十分なまま作成してしまうと、かえってご家族間に争いの種を残してしまうことにもなりかねません。
大東法律事務所では、ご相談者様のお気持ちを丁寧に伺い、法的なリスクを洗い出した上で、将来の紛争を予防するための最適な遺言書作成をサポートいたします。
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
▼お問い合わせはこちら▼