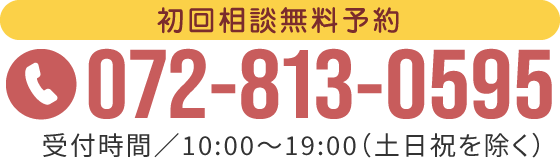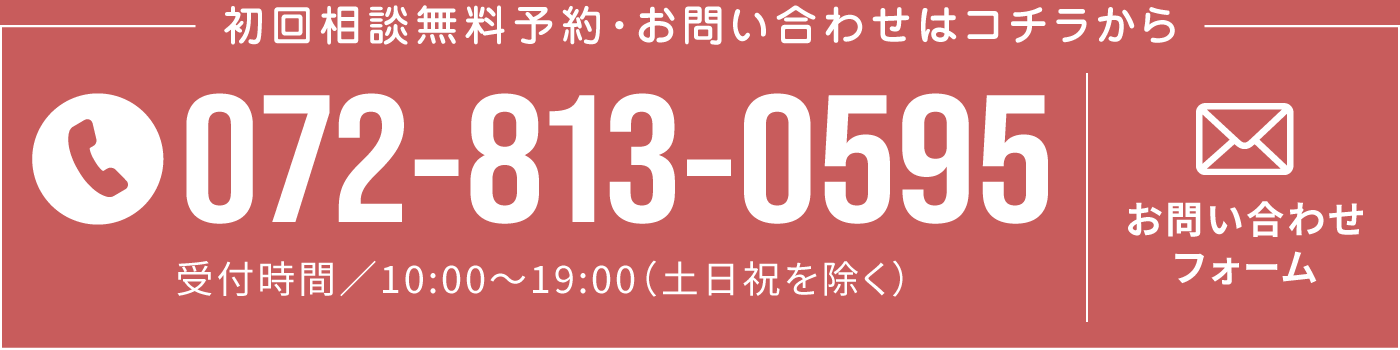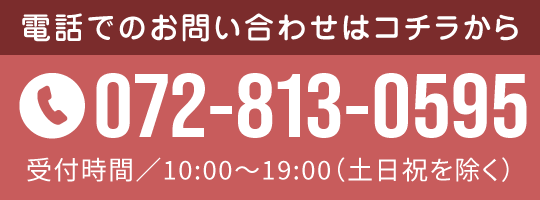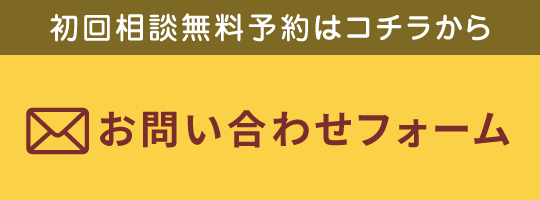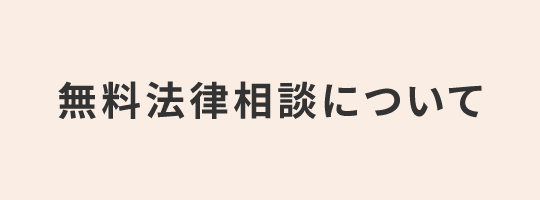このページの目次
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に減額したケース

本件は、被相続人が亡くなった後、長年居住していた不動産の取得をめぐり、他の相続人との間で代償金の金額が争われた事例です。
弁護士が適切な資料収集と査定を行い、調停手続きを通じて交渉を進めたことで、依頼者にとって大幅に有利な条件で不動産の取得が実現しました。
🔍 依頼者の状況
依頼者:山田一郎さん(仮名)/50代男性
相続関係:被相続人(父)、母と子3人による相続
主な争点:遺産の評価額・代償金の金額
山田一郎さんは、結婚後約20年にわたって父名義の自宅に居住しており、数年前には数百万円をかけてリフォームも行っていました。
父が亡くなり、相続が発生したところ、他の相続人(母・妹2名)からは、
「その家を売るか、お金を払って取得してほしい」
との要求されていました。
一郎さんはどう対応すればよいか分からず、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
①適正な評価を基に主張を構築
受任後、遺産内容の精査を開始しました。
- 預金・株式:金融機関から残高証明を取得
- 不動産:法務局や市役所から資料を取得し、不動産業者と連携して査定
その結果、
- 遺産総額:約1,000万円
- 居住不動産の価値:約300万円
と評価し、不動産を取得する代わりに150万円の代償金支払いを主張しました。
② 相手方との交渉と調停申立
他の相続人側は、
- 遺産総額:約900万円
- 居住不動産の価値:約600万円
として、450万円の代償金支払いを要求してきました。
交渉が平行線をたどったため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
③ 丁寧な資料提出と主張の継続
調停において、当方は、不動産の査定資料やリフォーム費用の証拠などを提出しました。
特に「長年の居住」や「自己負担での改修」を重視し、生活実態に即した主張を丁寧に重ねました。
また、調査の過程で他の相続人の一人が生前に贈与を受けていたことが判明したため、これが特別受益に該当するとして、その分を相手方が取得した遺産として計算するよう求めました。
💡 解決結果|150万円で自宅を取得
調停の結果、相手方も当方の評価を受け入れ、
150万円の代償金支払いにより居住不動産を取得することで合意が成立しました。
不当に高額な請求を避け、依頼者にとって納得のいく結果となりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続では、「住んでいる家をどうするか」が大きな争点となることがよくあります。
本件のように長く住んでいた場合でも、法定相続分に基づき代償金を請求されることがあります。
そのため、
- 遺産の正確な評価
- リフォームや居住実態の証明
- 特別受益の確認
などを行い、法的根拠をもって主張することが重要です。
早い段階での相談が、将来のトラブルを防ぎます。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 住んでいる家を相続したいが、他の相続人と話が進まない方
- 高額な代償金を請求されて困っている方
- 相続財産に不動産が含まれており、評価に疑問がある方
- 自分でリフォームした家を守りたい方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。