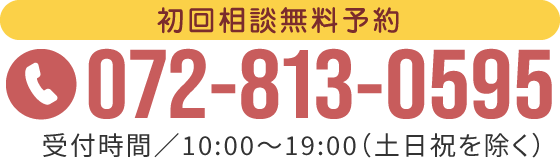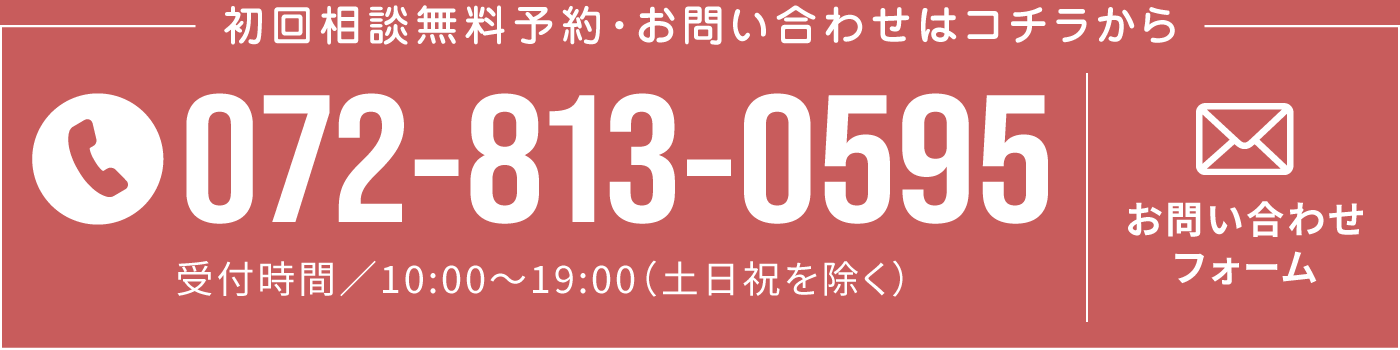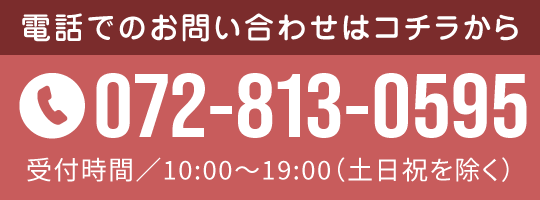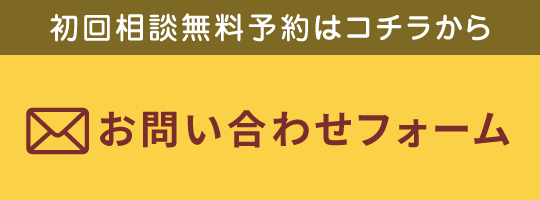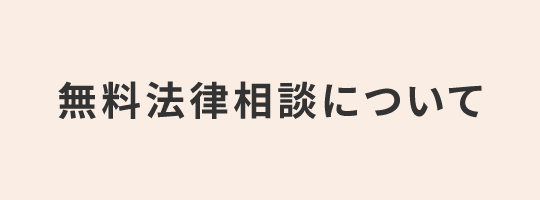このページの目次
【解決事例】遺留分請求に対し、生前の多額な援助を立証し請求を退けた事例

本件は、遺言により全財産を相続した兄に対し、弟から遺留分侵害額請求訴訟が提起された事例です。弁護士が裁判手続きを通じて弟への多額の生前贈与を立証したことで、勝訴的和解を成立させることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 田中 健一(仮名)
- 相続関係: 被相続人(母)、兄弟2名による相続
- 主な争点: 特別受益の存在と、遺留分侵害の有無
依頼者の田中健一さん(仮名)は、お母様を亡くされました。お母様は生前、「全財産を健一さんに相続させる」という内容の遺言書を遺しており、その遺産は不動産や預金を合わせて約2000万円にのぼりました。
ところが、遺言の内容を知った弟の修二さん(仮名)から、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を支払うよう請求されました。
健一さんは生前お母様から「弟にはたくさんのお金の援助をしてきた」と聞かされていましたが、修二さんは認めません。話し合いでの解決は難航し、ついに修二さんは健一さんを被告として遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。
健一さんはどう対応すればよいか分からず、大変お困りの状況で大東法律事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、弟の修二さんに対するお母様からの生前贈与(特別受益)の事実を明らかにし、健一さんの正当な権利を守るために以下の対応を行いました。
① 被相続人の預金履歴の調査
まず、健一さんからお聞きした「弟への多額の援助」という情報を元に、亡きお母様の預金履歴を金融機関から取り寄せ、精査しました。その結果、弟の修二さんと同居されていた時期に、使途の分からない多額の出金が繰り返されていることが確認できました。
② 裁判所を通じた相手方の預金履歴の開示請求
お母様の口座から多額の出金があったとしても、それだけではそのお金が修二さんに渡ったことの直接的な証拠にはなりません。そこで、弁護士は裁判所に対し、「調査嘱託」を申し立て、銀行に対して修二さん名義の預金口座の取引履歴を開示させるよう求めました。
③ 特別受益の主張と立証
裁判所を通じて開示された修二さんの預金履歴を分析した結果、お母様の口座から出金された時期とほぼ同じタイミングで、修二さんの口座に合計1500万円を超える多額の入金があったことが判明しました。
当事務所は、この事実をもって「修二さんは、遺産の前渡しといえる多額の生前贈与(特別受益)を受けており、その額は遺留分を大幅に上回るものである。したがって、健一さんが支払うべき遺留分は存在しない」と強く主張しました。
💡 解決結果
当事務所による特別受益の主張と立証の結果、裁判官も「修二さんの遺留分は生前の贈与によって既に満たされており、遺留分侵害額請求は認められない」との心証を示しました。
この心証を踏まえ、最終的には訴訟の早期円満解決の観点から、健一さんが修二さんへ解決金として100万円を支払うという内容で和解が成立しました。
もし弁護士に依頼せず、言われるがまま遺留分を支払っていれば、数百万単位の高額な支払いが必要となっていた可能性がありました。法的に特別受益を立証できたことで、健一さんは経済的な負担を大幅に軽減できただけでなく、長引く裁判のストレスからも解放されました。
💬 弁護士からのアドバイス
「遺留分を請求されたら、必ず支払わなければならない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本件のように、請求してきた相手方が被相続人から多額の生前贈与(家を建てる資金援助、事業資金の提供、多額の学費など)を受けていた場合、その金額を考慮することで、支払うべき遺留分の額を減額したり、場合によってはゼロにしたりすることも可能です。
「生前贈与の証拠がない」という場合でも、諦める必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、今回のように裁判所の手続きを通じて相手方の資料を開示させるなど、法的な手段を用いて証拠を収集することが可能です。他の相続人から遺留分を請求されてお困りの方は、ご自身の記憶だけで判断せず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 他の相続人から遺留分侵害額請求をされて、対応に困っている方
- 被相続人が、特定の相続人だけに多額の援助をしていた可能性がある方
- 「遺留分を支払え」と言われているが、その金額や根拠に納得できない方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。 相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。