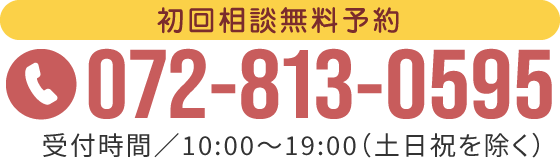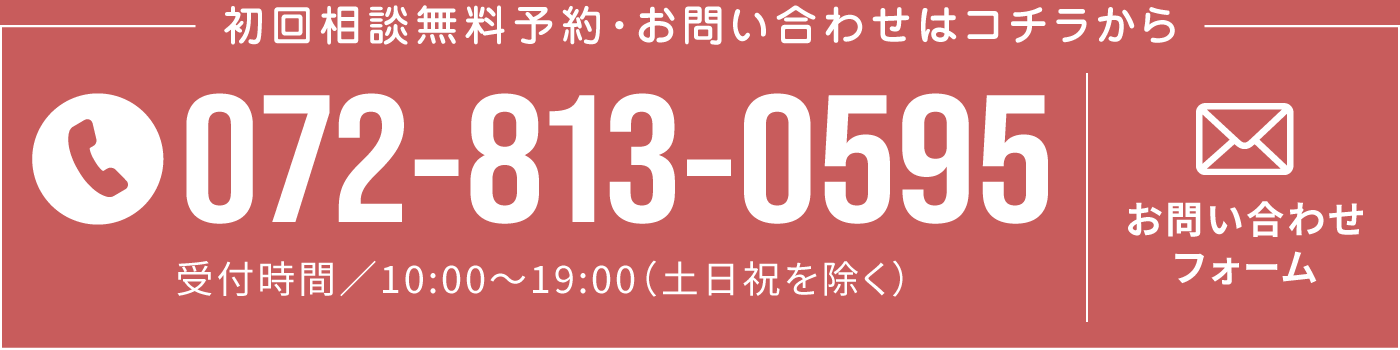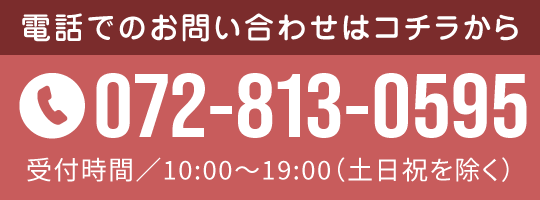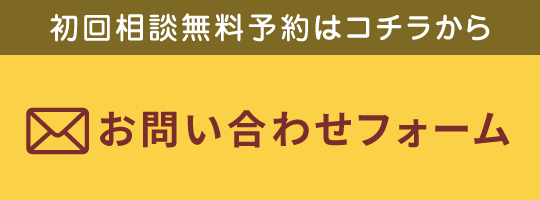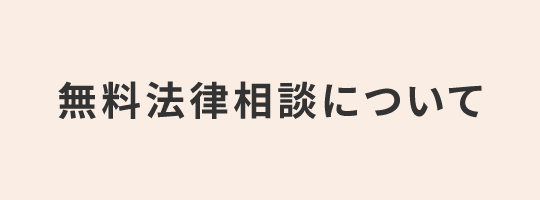「弟の自分には何もなかったのに、兄だけ親から家を買うお金を出してもらっていた…」 「そのことを無視して、兄が『遺産は法律通り半分ずつだ』と主張してきて納得できない」
相続が発生したとき、特定の相続人だけが生前に親から多額の援助を受けていたことが発覚し、不公平感から深刻なトラブルに発展するケースは非常に多くあります。
その不公平を解消するために、法律には「特別受益」という制度が用意されています。この記事では、特別受益とは何か、どうすればあなたの相続分を公平に計算できるのか、そしてそれを主張するための具体的な方法と証拠について、分かりやすく解説します。
このページの目次
「特別受益」とは?
特別受益とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受け取った、遺産の前渡しと評価できるような特別な利益(贈与)のことです 。
相続は、残された相続人の間で公平に行われるべきです。もし特定の子供だけが多額の援助を受けていたのに、残った遺産まで他の子供と平等に分けるとしたら、著しく不公平な結果になってしまいます。
そこで民法は、この特別受益を一度遺産に加算して(これを「持ち戻し」と言います)、その上で各相続人の取り分を計算し直すことで、相続人間の公平を図る仕組みを設けているのです 。
どのような贈与が「特別受益」にあたるのか?
すべての生前贈与が特別受益になるわけではありません。数万円程度のお小遣いや、扶養義務の範囲内とみなされる学費の援助などは、通常、特別受益にはあたりません。
特別受益と判断されやすいのは、以下のような「遺産の前渡し」といえる性質を持つ、まとまった金額の贈与です。
- 結婚や養子縁組のための贈与
- 結納金、持参金、結婚支度金など
- 結納金、持参金、結婚支度金など
- 生計の資本としての贈与
- 住宅購入資金の援助
- 事業を始めるための開業資金の援助
- 高額な学費(他の兄弟と比べて著しく高額な場合)
- 生命保険金
受取人が特定の相続人の場合、遺産総額との比較などから特別受益とみなされることがあります。
【計算例】特別受益がある場合の相続分の計算方法
特別受益を考慮した相続分の計算は、「持ち戻し計算」という方法で行います。言葉だけでは分かりにくいので、具体的な例で見てみましょう。
【設例】
被相続人:父
相続人:長男、次男の2人
相続開始時の遺産:5,000万円
長男が受けていた特別受益:1,000万円(住宅購入資金)
ステップ1:みなし相続財産を計算する
まず、相続開始時の遺産に、特別受益の額を加算します。これを「みなし相続財産」と呼びます。
5,000万円(実際の遺産) + 1,000万円(長男の特別受益) = 6,000万円(みなし相続財産)
ステップ2:法定相続分を計算する
次に、みなし相続財産を元に、各相続人の本来の法定相続分を計算します。
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
この場合、長男・次男それぞれの法定相続分は3,000万円となります。
ステップ3:実際の取得分を計算する
最後に、特別受益を受けていた相続人の取り分から、その受益額を差し引きます。
- 長男の取得分
3,000万円(法定相続分) - 1,000万円(特別受益) = 2,000万円 - 次男の取得分
3,000万円(法定相続分)
【結論】
このケースでは、実際の遺産5,000万円のうち、長男が2,000万円、次男が3,000万円を相続することで、公平な遺産分割が実現します。もし特別受益を考慮しないと、それぞれ2,500万円ずつの取得となり、次男は著しく不利益を被ることになります。
特別受益を主張するために必要な「証拠」
特別受益を主張する上で最も重要なのが、贈与の事実を客観的に証明する「証拠」です。相手が「そんなお金はもらっていない」と否定した場合、証拠がなければあなたの主張を認めてもらうことは困難です。
有効な証拠の例
- 銀行の取引履歴、預金通帳の写し
親の口座から兄の口座へ直接送金された記録など。 - 贈与契約書
親と兄の間で作成された書類。 - 被相続人の日記、手紙、メモ
「長男に家を買うため1,000万円渡した」といった記述。 - 他の親族や第三者の証言
贈与の事実を知っている親族などの証言。 - 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
親から不動産そのものが贈与されている場合。
特別受益を主張するための3つのステップ
ステップ1:遺産分割協議で主張する
まずは相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の場で、集めた証拠を提示し、特別受益の持ち戻し計算をすべきだと主張します。ここで相手が事実を認め、計算方法に合意すれば、その内容で遺産分割協議書を作成します。
ステップ2:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
話し合いで相手が贈与の事実を認めない、あるいは持ち戻し計算を拒否する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員という中立な第三者が間に入り、法的な観点から双方の主張を聞き、解決案を探ります。
ステップ3:調停不成立の場合は「審判」へ移行
調停でも合意に至らない場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が全ての証拠や主張を審査し、特別受益の有無や金額、最終的な遺産の分割方法について法的な判断を下します。
特別受益の主張を弁護士に依頼するメリット
特別受益の主張は、法的な専門知識と交渉力が必要となる、非常に難しい手続きです。
- 法的に有効な主張の組み立て
どのような贈与が特別受益にあたるのか、集めた証拠が法的にどの程度の価値を持つのかを専門家の視点で判断し、的確な主張を組み立てます 。 - 相手との交渉代理
弁護士が代理人として交渉することで、感情的になりがちな兄弟間の話し合いを冷静に進めることができます。直接対峙する精神的なストレスも大幅に軽減されます 。 - 調停・審判での強力なサポート
法的手続きに移行した場合でも、あなたの代理人として法廷で論理的な主張と立証を行い、あなたの正当な権利が認められるよう最後までサポートします 。
まとめ:不公平を正し、あなたの正当な権利を守るために
「兄だけずるい」という感情は、決して間違っていません。法律は、あなたのその不公平感を正すための「特別受益」という武器を用意してくれています。
しかし、その武器を正しく使い、あなたの権利を実現するためには、専門的な知識と戦略が不可欠です。問題を一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまう前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所では、相続問題に関する初回のご相談は無料で承っております。あなたの状況を詳しくお伺いし、特別受益を主張できる可能性や、今後の具体的な進め方についてアドバイスいたします。