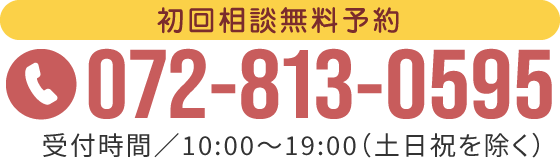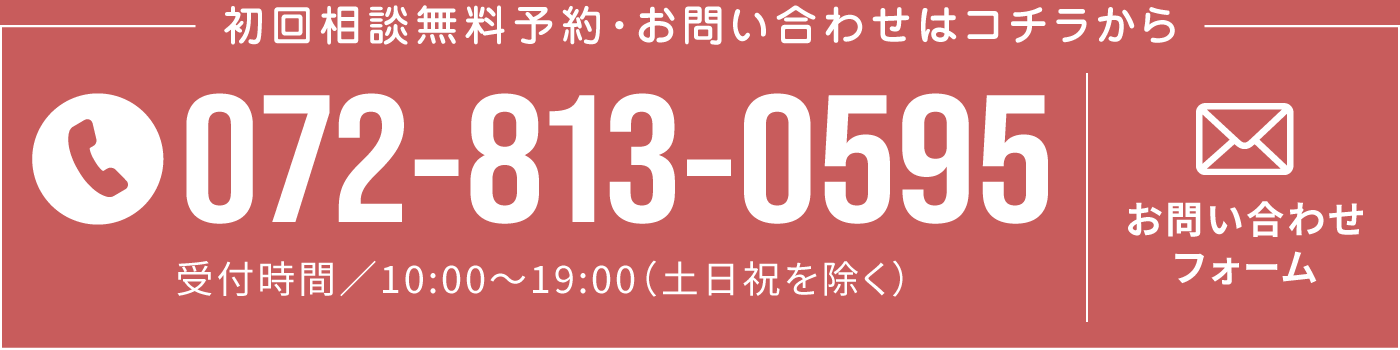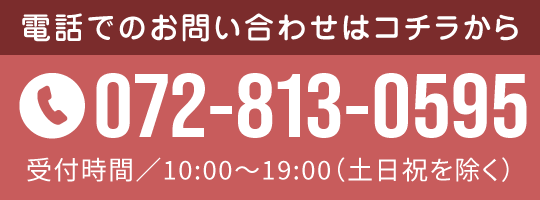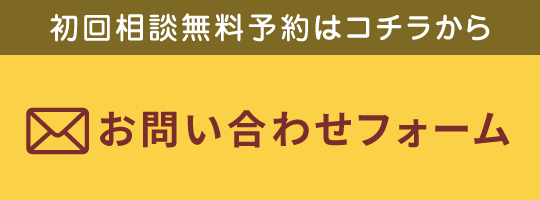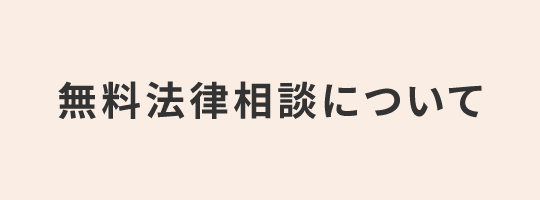「相続手続きを進めたいのに、相続人の一人と全く連絡が取れない…」
「疎遠だったり、どこに住んでいるかも分からなかったりする場合、どうすればいいのだろう?」
遺産分割協議は、法律上、相続人“全員”の合意がなければ成立しません 。たった一人でも連絡が取れない相続人がいると、預金の解約も、不動産の名義変更や売却も、一切の手続きが完全にストップしてしまいます。
この問題を放置すると、相続税の申告で不利になるだけでなく、残された財産の管理を巡って新たなトラブルが発生する可能性もあります。
この記事では、このような八方塞がりの状況を打開するため、連絡が取れない相続人を調査する方法から、法的な手続きを経て遺産分割を完了させるまでの全手順を解説します。
このページの目次
連絡が取れない相続人を放置するリスク
まず、なぜこの問題を放置してはいけないのか、具体的なリスクを理解することが重要です。
預貯金の解約・引き出しが一切できない
金融機関は、相続人全員の同意(遺産分割協議書と全員の印鑑証明書)がなければ、被相続人の口座の解約や払い戻しに一切応じません。
不動産の名義変更や売却ができない
不動産を誰が相続するのか、あるいは売却して現金で分けるのかを決めるには、やはり相続人全員の合意が必要です。手続きが滞れば、誰も住まない実家を売却することもできず、管理コストだけがかかり続ける事態になりかねません 。
共有財産の管理負担と新たなトラブルの火種となる
遺産分割が完了するまで、不動産などの遺産は相続人全員の共有財産となります。
空き家になった実家の固定資産税や管理費は誰が支払うのか?修繕が必要になった場合の費用負担はどうするのか?など、新たな金銭トラブルの火種となり、相続人間の関係をさらに悪化させる可能性があります。
相続税の申告・納税が遅れ、ペナルティが発生する
相続税の申告・納税期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。遺産分割がまとまらないと、税額を軽減できる特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)が使えず、本来より多くの税金を納めることになる場合があります。
連絡が取れない相続人がいる場合の対応フロー
連絡が取れない相続人を調査する方法から、法的な手続きを経て遺産分割を完了させるまでの全手順を、ステップ・バイ・ステップで具体的に解説します。
ステップ1:戸籍等を取得し現在の住所を突き止める
遺産分割協議を進めるための第一歩は、連絡が取れない相続人の現在の住所を正確に把握することです。感情的に「探したくない」と思うかもしれませんが、法的手続きを進める上でもこの調査は不可欠です。
戸籍の附票(こせきのふひょう)を取得する
最も基本的かつ強力な調査方法が、「戸籍の附票」を取得することです 。
- 戸籍の附票とは?
その人がその戸籍に入ってから現在までの住所の移り変わりが記録された公的な書類です。本籍地の役所で管理されています。 - どうやって取得する?
相続人であれば、他の相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を請求する権利があります。連絡が取れない相続人の本籍地を戸籍謄本でたどり、その役所に対して郵送で請求することが可能です。
海外在住の可能性がある場合:外務省への所在調査
もし相続人が海外に住んでいる可能性がある場合は、外務省に対して「所在調査」を依頼することができます 。ただし、これは相手が日本国籍で、現地の日本大使館などに在留届を出している場合に有効な手段です。
ステップ2:住所が判明したら、手紙で連絡を取る
調査によって住所が判明したら、次は慎重にコンタクトを試みます。
手紙で連絡する際のポイント
- 高圧的な態度は避ける
突然の連絡に相手が警戒しないよう、丁寧で穏やかな文面を心がけます。 - 相続が発生した事実と、協力が必要な理由を明確に伝える
遺産分割協議には全員の参加が必須であることを説明します。 - 財産目録を同封する
財産を隠していると疑われないよう、判明している全ての財産をリスト化して開示し、誠実な姿勢を見せることが重要です 。 - 返信期限を設ける
「〇月〇日までにご返信ください」と期限を明記します。 - 記録が残る方法で送る
相手が受け取ったかを確認できる「内容証明郵便」や「特定記録郵便」を利用するのが望ましいです 。
ステップ3:連絡がない・所在不明の場合は法的手続に移行する
調査を尽くしても住所が分からない、あるいは手紙を送っても完全に無視される場合は、家庭裁判所での法的な手続きに移行します。ここからは専門的な知識が不可欠となります。
ケース1:住所は判明しているが、連絡を無視される場合 → 「遺産分割調停」の申立て
手紙を送っても返信がなく、電話にも出ないなど、意図的に協議を拒否されている場合に有効な手段です 。
- 遺産分割調停とは?
家庭裁判所で、調停委員という中立な第三者を交えて遺産分割について話し合う手続きです。裁判所から相手の住所へ正式な呼出状が送達されるため、無視を続けていた相続人も対応せざるを得なくなる効果が期待できます 。 - 相手が調停に出席しない場合
相手が正当な理由なく調停に出頭しない場合、調停は不成立となります。その場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、遺産の分割方法を決定します 。これにより、相手の協力が得られなくても、法的に遺産分割を完了させることが可能です。
ケース2:生きていることは確かだが、所在不明の場合 → 「不在者財産管理人」の選任
住所が不明だが、死亡している可能性は低いという場合に利用する制度です 。
- 不在者財産管理人とは?
行方不明者に代わって財産を管理する人を、家庭裁判所が選任する制度です。選任された管理人(多くは弁護士などの専門家)が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。 - 手続きの流れ
- 利害関係人(他の相続人など)が、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に選任を申し立てます。
- 裁判所が審査の上、不在者財産管理人を選任します。
- 遺産分割協議を行うには、管理人が別途「権限外行為許可」を裁判所に申し立て、許可を得る必要があります 。
- 許可が出れば、管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を成立させることができます。
ケース3:7年以上、完全に音信不通で生死不明の場合 → 「失踪宣告」の申立て
7年以上にわたって全く連絡が取れず、生きているかどうかも分からない場合に利用する制度です 。
- 失踪宣告とは?
家庭裁判所の手続きを経て、その行方不明者を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。 - 効果
失踪宣告が認められると、その相続人は死亡したものとして扱われるため、残りの相続人だけで遺産分割協議を進めることができます。もし失踪者に子がいれば、その子が代襲相続人となります。
遺産分割手続を弁護士に依頼するメリット
ここまで読んでいただくと、連絡が取れない相続人がいる場合の手続きが、いかに複雑で時間と手間がかかるかお分かりいただけたかと思います。特に家庭裁判所での手続きは、ご自身で進めるのは非常に困難です。
弁護士に依頼することで、これらの問題を一挙に解決できます。
メリット1:煩雑な調査手続きをすべて代行
時間のかかる戸籍の附票の取り寄せなど、相続人の調査を全て任せることができます 。
メリット2:複雑な裁判所手続きを正確かつ迅速に進められる
「遺産分割調停」や「不在者財産管理人の選任」、「失踪宣告」といった専門的な申立て手続きを、あなたの代理人として的確に行います 。
メリット3:精神的な負担から解放される
連絡が取れない相手へのアプローチや、裁判所とのやり取りといったストレスのかかる業務から解放され、あなたは本来の生活に集中できます 。
メリット4:円満かつ法的に妥当な解決を目指せる
弁護士という中立的な専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、法に基づいた公平な遺産分割案を作成し、スムーズな解決へと導きます。
問題を先送りにせず、今すぐ専門家にご相談を
連絡が取れない相続人がいる問題は、時間だけでは解決しません。むしろ、放置すればするほど法的なリスクは高まり、解決はより困難になります。
「どこから手をつけていいか分からない」「自分でやってみたが限界だ」と感じたら、それは専門家の助けを借りるべきサインです。
大東法律事務所事務所では、相続問題に関する初回のご相談は無料で承っております。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、今後どのような手続きが必要か、解決までの道筋を分かりやすくご説明します。この複雑な問題を解決し、あなたの大切な権利を守るため、まずはお気軽にお問い合わせください。