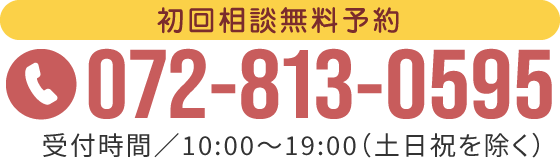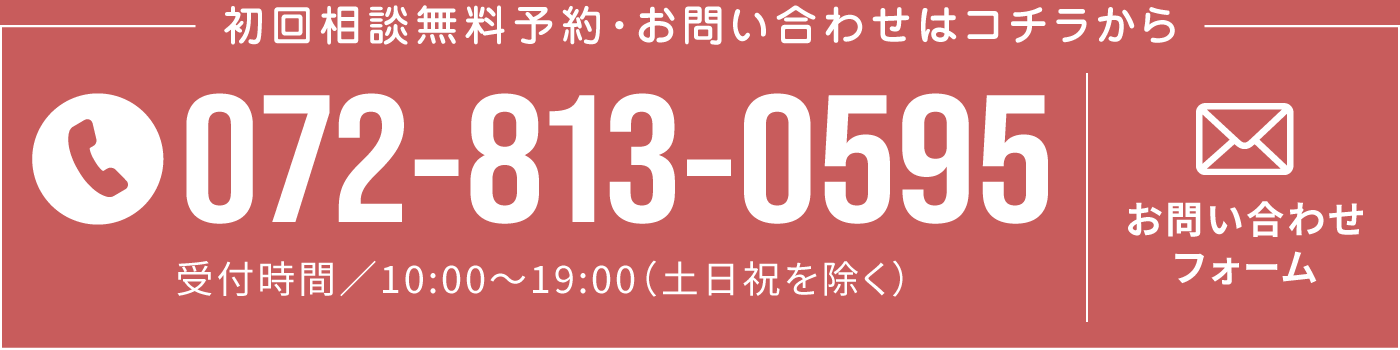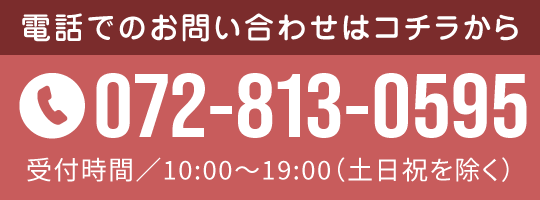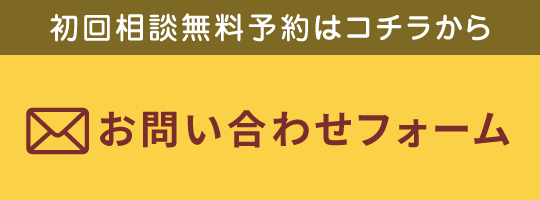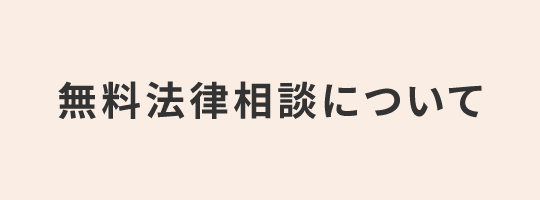解決事例
【解決事例】遺留分請求に対し、生前の多額な援助を立証し請求を退けた事例
【解決事例】遺留分請求に対し、生前の多額な援助を立証し請求を退けた事例

本件は、遺言により全財産を相続した兄に対し、弟から遺留分侵害額請求訴訟が提起された事例です。弁護士が裁判手続きを通じて弟への多額の生前贈与を立証したことで、勝訴的和解を成立させることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 田中 健一(仮名)
- 相続関係: 被相続人(母)、兄弟2名による相続
- 主な争点: 特別受益の存在と、遺留分侵害の有無
依頼者の田中健一さん(仮名)は、お母様を亡くされました。お母様は生前、「全財産を健一さんに相続させる」という内容の遺言書を遺しており、その遺産は不動産や預金を合わせて約2000万円にのぼりました。
ところが、遺言の内容を知った弟の修二さん(仮名)から、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を支払うよう請求されました。
健一さんは生前お母様から「弟にはたくさんのお金の援助をしてきた」と聞かされていましたが、修二さんは認めません。話し合いでの解決は難航し、ついに修二さんは健一さんを被告として遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。
健一さんはどう対応すればよいか分からず、大変お困りの状況で大東法律事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、弟の修二さんに対するお母様からの生前贈与(特別受益)の事実を明らかにし、健一さんの正当な権利を守るために以下の対応を行いました。
① 被相続人の預金履歴の調査
まず、健一さんからお聞きした「弟への多額の援助」という情報を元に、亡きお母様の預金履歴を金融機関から取り寄せ、精査しました。その結果、弟の修二さんと同居されていた時期に、使途の分からない多額の出金が繰り返されていることが確認できました。
② 裁判所を通じた相手方の預金履歴の開示請求
お母様の口座から多額の出金があったとしても、それだけではそのお金が修二さんに渡ったことの直接的な証拠にはなりません。そこで、弁護士は裁判所に対し、「調査嘱託」を申し立て、銀行に対して修二さん名義の預金口座の取引履歴を開示させるよう求めました。
③ 特別受益の主張と立証
裁判所を通じて開示された修二さんの預金履歴を分析した結果、お母様の口座から出金された時期とほぼ同じタイミングで、修二さんの口座に合計1500万円を超える多額の入金があったことが判明しました。
当事務所は、この事実をもって「修二さんは、遺産の前渡しといえる多額の生前贈与(特別受益)を受けており、その額は遺留分を大幅に上回るものである。したがって、健一さんが支払うべき遺留分は存在しない」と強く主張しました。
💡 解決結果
当事務所による特別受益の主張と立証の結果、裁判官も「修二さんの遺留分は生前の贈与によって既に満たされており、遺留分侵害額請求は認められない」との心証を示しました。
この心証を踏まえ、最終的には訴訟の早期円満解決の観点から、健一さんが修二さんへ解決金として100万円を支払うという内容で和解が成立しました。
もし弁護士に依頼せず、言われるがまま遺留分を支払っていれば、数百万単位の高額な支払いが必要となっていた可能性がありました。法的に特別受益を立証できたことで、健一さんは経済的な負担を大幅に軽減できただけでなく、長引く裁判のストレスからも解放されました。
💬 弁護士からのアドバイス
「遺留分を請求されたら、必ず支払わなければならない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本件のように、請求してきた相手方が被相続人から多額の生前贈与(家を建てる資金援助、事業資金の提供、多額の学費など)を受けていた場合、その金額を考慮することで、支払うべき遺留分の額を減額したり、場合によってはゼロにしたりすることも可能です。
「生前贈与の証拠がない」という場合でも、諦める必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、今回のように裁判所の手続きを通じて相手方の資料を開示させるなど、法的な手段を用いて証拠を収集することが可能です。他の相続人から遺留分を請求されてお困りの方は、ご自身の記憶だけで判断せず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 他の相続人から遺留分侵害額請求をされて、対応に困っている方
- 被相続人が、特定の相続人だけに多額の援助をしていた可能性がある方
- 「遺留分を支払え」と言われているが、その金額や根拠に納得できない方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。 相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】熟慮期間経過後の相続放棄|疎遠だった夫の死後、約2000万円の借金が発覚したが、無事相続放棄が認められたケース
【解決事例】熟慮期間経過後の相続放棄|疎遠だった夫の死後、約2000万円の借金が発覚したが、無事相続放棄が認められたケース

本件は、死亡から3ヶ月の熟慮期間が過ぎた後に被相続人が多額の借金を負っていたことが判明し、相続放棄を行った事例です。被相続人が借金を負っていたことを知ることができなかった特別な事情を丁寧に主張することで、無事相続放棄が認められました。
🔍 依頼者の状況
- ご相談者: 鈴木良子さん(仮名)、鈴木健一さん(仮名)
- 相続関係: 被相続人(夫)、妻と子による相続
- 主な争点: 熟慮期間(死亡を知ってから3ヶ月)経過後の相続放棄の可否
鈴木良子さん(妻)と健一さん(子)は、鈴木太郎さん(夫・父)と長年別居しており、生前の交流は年に数回食事をする程度でした 。 そのため、太郎さんの財産状況については全く知らされていませんでした 。
そんな中、太郎さんが亡くなられたとの連絡が入りました。
太郎さんの葬儀後、健一さんが遺品を整理しましたが、太郎さんが負債を負っていることをうかがわせる書類は何も発見されませんでした。また、 他の親族と連絡を取り合っても、太郎さんに債務があるとの話は一切出てきませんでした。
そのため、良子さんと健一さんは特に相続放棄の必要はないものと考え、手続きをしないまま3ヶ月が経過してしまいました。
しかしその後、突然、債権回収会社から約2000万円もの高額な借金の返済を求める通知書が届いたのです。 予期せぬ負債の存在を知り、良子さんと健一さんは大きなショックと不安を抱え、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
突然の高額な借金の請求に動揺されているお二人の話を丁寧に伺い、相続放棄が認められる可能性が十分にあると判断し、迅速に対応しました。
① 詳細な事情の聴取と方針の決定
まず、弁護士は良子さんと健一さんから、太郎さんとの生前の関係性 、遺品整理の具体的な状況 、他の相続人とのやり取り 、そして借金が発覚した経緯について 、極めて詳細に聞き取りを行いました。
その結果、お二人には「相続財産(特に負債)の存在を認識することが著しく困難であった」という特別な事情があると判断し、相続放棄の熟慮期間の起算点を「借金の存在を現実に知った日」とすべきであると主張する方針を固めました 。
② 「特別な事情」を具体的に記載した上申書の作成
家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうため、通常の申述書に加え、本件の特殊な事情を詳細に説明する「上申書」を作成・提出しました。
上申書には、
- 長年の別居により、被相続人の生活状況や財産を全く知る由もなかったこと
- 遺品整理の際も、借金に関する資料は一切発見されなかったこと
- 郵便物の転送手続き後も、債権者からの督促状などが届くことはなかったこと
- 債権回収会社からの通知書によって、初めて約2000万円という莫大な負債の存在を知ったこと
といった客観的な事実を時系列に沿って具体的に記述し、「熟慮期間の起算日は、債権回収会社からの通知を受け取った日と解釈されるべきである」と法的に主張しました 。
③ 家庭裁判所への申述と受理
作成した相続放棄申述書と上申書を、速やかに管轄の家庭裁判所に提出しました。
当事務所の主張が認められ、良子さんと健一さんの相続放棄の申述は無事に受理されました。
💡 解決結果
当事務所の主張が全面的に認められ、家庭裁判所は良子さんと健一さんの相続放棄の申述を受理しました。
これにより、良子さんと健一さんは、被相続人が遺した約2000万円もの高額な借金を一切支払う義務がなくなりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。これを「熟慮期間」といいます。
しかし、今回のケースのように、被相続人と疎遠であったために財産状況を全く知らず、相続財産の調査を尽くしてもなお債務の存在を認識できなかったような「特別な事情」がある場合には、死亡の事実を知ってから3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。その場合、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時」から起算される、というのが判例の考え方です。
重要なのは、「知らなかった」とただ主張するのではなく、「なぜ知ることができなかったのか」を、客観的な証拠に基づいて具体的に、かつ説得的に裁判所に説明することです。遺品整理の状況や生前の関係性などを詳細に主張する必要があります。
熟慮期間が過ぎてしまったと諦めてしまう前に、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。ご自身のケースが「特別な事情」にあたるかどうかを法的な観点から的確に判断し、最善の解決策をご提案いたします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 亡くなった親族の死後3ヶ月以上経ってから、金融機関や債権回収会社から借金の督促状が届いた方
- 遺産分割協議を進めていたら、後から高額な負債があることが判明した方
- 疎遠だった親族が亡くなり、財産状況が全く分からず困っている方
- 相続財産の調査を自分で行ったが、借金があるのかないのかはっきりせず、相続放棄をすべきか判断に迷っている方
当事務所では、相続放棄に関する初回のご相談は無料となっております。
相続放棄でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】異父兄の相続で戸籍に不備|失踪宣告により単独相続を実現したケース
【解決事例】異父兄の相続で戸籍に不備|失踪宣告により単独相続を実現したケース

本件は、兄の相続人は自分だけだと思っていた依頼者が、兄と異父兄弟であり他の相続人が存在する可能性があることが判明し、最終的に失踪宣告を通じて単独相続を実現した事例です。
複雑な事情でも、弁護士が法的手段を駆使し、依頼者にとって納得できる形で解決に導くことができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:鈴木春子さん(仮名)/80代女性
- 被相続人(兄):鈴木健一さん(仮名)
- 問題となった第三者(兄の父):鈴木一郎さん(仮名)
- 主な争点:相続人の確定・戸籍不備・失踪宣告手続
鈴木春子さんは、長年兄・健一さんと二人暮らしをし、介護も行ってきました。
健一さんからは「財産は全部お前にやる」と言われていたため、遺言なしで相続人は自分だけだと信じていました。
しかし、健一さんの死後に相続手続を進めようとしたところ、健一さんと春子さんは異父兄弟であることが判明し、さらに健一さんの父・一郎さんについて一切の情報がなかったため、相続人が不明確という重大な問題が浮上しました。
この想定外の状況に、春子さんは途方に暮れ、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 戸籍の調査
まずは、健一さんの父・一郎さんについて情報を得るため、健一さんの生まれてから亡くなるまでの間の戸籍を取得しました。しかし、
- 健一さんの戸籍には一郎さんの名前・生年月日以外の情報が記載されておらず
- 役所に問い合わせても詳細情報は得られませんでした
健一さんの年齢からして、父親である一郎さんの推定年齢は100歳前後となるため、既に亡くなられている可能性が高いものの、記録上はこれを明らかにする方法がありませんでした。
② 銀行との協議
仮に一郎さんが生存していれば相続人となり、万が一亡くなっていてもその子(健一さんの兄弟)が相続人となる可能性がありました。
そこで、「一郎さんの生死が不確定なため、失踪宣告を行う予定」「健一さんに他に兄弟がいるかは不明だが、戸籍上調査のしようがないため、失踪宣告後は春子さんの単独相続を認めてほしい」と銀行と話し合い、方針を協議しました。
その結果、銀行からは
「家庭裁判所で一郎さんの失踪宣告が下りれば、春子さんの単独相続で手続きを進めてよい」
という合意を得られました。
③ 失踪宣告の申立
依頼者の聞き取りにより、当事務所は事実関係を整理し、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行いました。
家庭裁判所での調査官面談にも同席し、事実関係を詳細に伝え、失踪宣告が必要であることを説明しました。
その結果、健一さんの父・一郎さんについて失踪宣告が認められ、法的に死亡とみなされました。
最終的に、失踪宣告の判決書を銀行に提出し、春子さんが単独で相続手続きを完了することができました。
💡 解決結果|失踪宣告を経て相続手続きを完了
- 戸籍の不備がある中、失踪宣告という法的措置を的確に活用
- 一郎さんを法律上「死亡」と扱うことで、単独相続が認められた
- 長年介護してきた兄の財産を、春子さんが無事に受け継ぐことができた
💬 弁護士からのアドバイス
相続で戸籍に不備があったり、意外な相続人がいる疑いがある場合は、そのまま手続きを進めてはいけません。
一方、失踪宣告や金融機関との事前協議などの法的手段を用いることで、想定外の問題にも対応できる可能性があります。
また、健一さんのように「口頭だけで財産を約束」するのでは不十分です。
遺言書を残しておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことが非常に重要です。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 相続人が誰か不明で戸籍調査が必要な方
- 戸籍に書かれていない親族がいる可能性がある方
- 生死不明の親族がいて相続ができない方
- 遺言なしで相続が始まりトラブルになりそうな方
当事務所では、相続に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【解決事例】音信不通だった姉の相続|1年以上経過後も放棄が認められたケース
【解決事例】音信不通だった姉の相続|1年以上経過後も放棄が認められたケース

本件は、亡くなった姉の相続について突然請求書が届き、1年以上経過していたものの、相続放棄が認められたケースです。
弁護士が相続人調査と時期的な要件を整理し、裁判所に対して明確な説明を行うことで、依頼者にとって不当な負担を回避することができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:70代男性
- 相続関係:被相続人(姉)、弟による単独相続
- 主な争点:相続人調査・相続放棄・熟慮期間の起算時期
依頼者には年上の姉がいましたが、30代の頃から疎遠となり、50代の頃の親の葬儀で顔を合わせて以降は、まったく連絡も取っていない状態が続いていました。
定年退職後は穏やかに暮らしていたものの、ある日突然、姉の「相続人」として自分宛に債権者から請求書が届きました。
電話で確認したところ、姉はすでに1年以上前に亡くなっていたことが判明し、
「あなたが相続人なので、支払ってください」
と説明されたため、どう対応すればよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 相続放棄が可能かどうかを判断
依頼者が姉の死を「最近知った」ばかりであることから、相続放棄が認められる可能性があると判断しました。
② 相続人調査の実施
姉に子(直系卑属:先順位相続人)がいるか不明だったため、戸籍収集による相続人調査を実施しました。
その結果、子はおらず、依頼者が相続人であることが確認できました。
③ 家庭裁判所への申述と事情説明
依頼者と姉の長期間にわたる疎遠な関係について丁寧にヒアリングを行い、
その経緯を文書化して相続放棄の申述書とあわせて裁判所へ提出しました。
→ 審査の結果、相続放棄は受理されました。
その後、債権者にも放棄が認められたことを通知し、請求は無事に止まりました。
💡 解決結果|1年以上経過後でも相続放棄が認められた
- 姉の死を知らなかったという事情が認められ、相続放棄が受理されました。
- 債権者からの請求も停止し、精神的・経済的な不安が解消されました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続放棄には原則として、
「相続の開始を知ったときから3か月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。
ただし、「死亡していたこと」「先順位相続人の放棄の事実」などを知らなかった正当な理由があれば、
3か月を過ぎていても放棄が認められることがあります。
そのためには、
- なぜ放棄が遅れたのか明確に説明できること
- 生活状況や人間関係の背景を丁寧に整理すること
がとても重要です。
事情説明に曖昧な点があると、相続放棄が認められないリスクもあるため、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 疎遠だった親族の相続人として突然請求を受けた方
- 相続放棄をしたいが、すでに3か月以上経っている方
- 相続人かどうか分からない・戸籍を集めるのが不安な方
- 借金や請求書が届き、困惑している方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】行方不明の相続人が判明|不在者財産管理人申立を活用し全員合意に至ったケース
【解決事例】行方不明の相続人が判明|不在者財産管理人申立を活用し全員合意に至ったケース

本件は、依頼者の姉が亡くなり、相続人の一人(甥)が連絡不通となったものの、不在者財産管理人の申立を経て相続手続きを進め、最終的に全員の合意によって遺産分割を完了した事例です。
法的制度を戦略的に用いることで、不安定な状況もしっかり収束させることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:佐藤悦子さん(仮名)/60代女性
- 被相続人(姉):佐藤美沙さん(仮名)
- 相続人:妹1名および甥姪11名(うち1名が行方不明)
- 主な争点:相続人の所在確認・不在者財産管理人申立・遺産分割協議
佐藤悦子さんの姉・美沙さんが亡くなり、預金・株式・不動産を含む遺産の相続が発生しました。
10名の甥姪とは連絡がつき協力的だったものの、甥の一人である山田五郎さん(仮名)だけが連絡不能で、所在も不明のままでした。
⚖ 当事務所の対応
① 相続人の所在確認調査
まず、戸籍と住民票を追い、五郎さんの最終的な住所を突き止めました。
しかし、現住所へ手紙を送るも五郎さんからの返答は得られませんでした。
現地の調査も行いましたが、現住所に居住している様子が窺えず、行方不明の状態が続きました。
② 不在者財産管理人の申立準備
本件では遺産に不動産が含まれるため、行方不明の相続人がいる状況で相続手続を進めるためには不在者財産管理人(=相続人が不在の状態で遺産管理・分配を補佐する第三者)を選任する必要がありました。
そこで、必要な書類を準備し、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任を申立てました。
③ 裁判所による調査と甥の所在判明
不在者財産管理人の選任手続の中で、裁判所による五郎さんの居所調査が行われました。
裁判所から職業安定所や警察機関に照会を行った結果、五郎さんの勤務先が判明しました。
その結果、五郎さん本人から連絡があり、所在と事情が確認されました。
④ 遺産分割協議と手続き完了
五郎さんとの話し合いの結果、五郎さんからも相続分通りで相続する合意が得られたため、不在者財産管理人選任申立を取り下げ、全相続人による遺産分割協議書を作成しました。
その後、預金解約・株式の現金化を含む一連の手続きを当事務所が代行し、相続分通りに遺産を配分して無事手続が完了しました。
💡 解決結果|相続人全員の合意により遺産分割が成立
行方不明の相続人がいる状態でも、制度を正しく使うことで相続手続を前に進め、無事遺産分割を成立させることができました。
また、遺産分割協議書作成から換価・配分まで弁護士に一貫してお任せ頂くことで、手続の負担を軽減することができました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続人の中に行方不明者が含まれる場合でも、不在者財産管理人制度を活用することで手続きを前進させることができます。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利とならない遺産分割案を策定し、財産目録を作成した上で裁判所の許可を得て協議に参加します。これにより、行方不明者の法定相続分は確保されつつ、相続手続きを円滑に進めることができます。
本件では、不在者財産管理人の手続の過程で本人の居所が判明したため、不在者財産管理人の選任を待つことなく、よりスムーズに話が進めることができました。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 相続人の一人が連絡つかず所在不明の方
- 相続人が多く、全員の同意が得にくい状況の方
- 遺産分割協議書の作成や換価手続に不安がある方
- 法的手段を使ってでも相続を速やかに進めたい方
当事務所では、相続に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に減額したケース
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に減額したケース

本件は、被相続人が亡くなった後、長年居住していた不動産の取得をめぐり、他の相続人との間で代償金の金額が争われた事例です。
弁護士が適切な資料収集と査定を行い、調停手続きを通じて交渉を進めたことで、依頼者にとって大幅に有利な条件で不動産の取得が実現しました。
🔍 依頼者の状況
依頼者:山田一郎さん(仮名)/50代男性
相続関係:被相続人(父)、母と子3人による相続
主な争点:遺産の評価額・代償金の金額
山田一郎さんは、結婚後約20年にわたって父名義の自宅に居住しており、数年前には数百万円をかけてリフォームも行っていました。
父が亡くなり、相続が発生したところ、他の相続人(母・妹2名)からは、
「その家を売るか、お金を払って取得してほしい」
との要求されていました。
一郎さんはどう対応すればよいか分からず、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
①適正な評価を基に主張を構築
受任後、遺産内容の精査を開始しました。
- 預金・株式:金融機関から残高証明を取得
- 不動産:法務局や市役所から資料を取得し、不動産業者と連携して査定
その結果、
- 遺産総額:約1,000万円
- 居住不動産の価値:約300万円
と評価し、不動産を取得する代わりに150万円の代償金支払いを主張しました。
② 相手方との交渉と調停申立
他の相続人側は、
- 遺産総額:約900万円
- 居住不動産の価値:約600万円
として、450万円の代償金支払いを要求してきました。
交渉が平行線をたどったため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
③ 丁寧な資料提出と主張の継続
調停において、当方は、不動産の査定資料やリフォーム費用の証拠などを提出しました。
特に「長年の居住」や「自己負担での改修」を重視し、生活実態に即した主張を丁寧に重ねました。
また、調査の過程で他の相続人の一人が生前に贈与を受けていたことが判明したため、これが特別受益に該当するとして、その分を相手方が取得した遺産として計算するよう求めました。
💡 解決結果|150万円で自宅を取得
調停の結果、相手方も当方の評価を受け入れ、
150万円の代償金支払いにより居住不動産を取得することで合意が成立しました。
不当に高額な請求を避け、依頼者にとって納得のいく結果となりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続では、「住んでいる家をどうするか」が大きな争点となることがよくあります。
本件のように長く住んでいた場合でも、法定相続分に基づき代償金を請求されることがあります。
そのため、
- 遺産の正確な評価
- リフォームや居住実態の証明
- 特別受益の確認
などを行い、法的根拠をもって主張することが重要です。
早い段階での相談が、将来のトラブルを防ぎます。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 住んでいる家を相続したいが、他の相続人と話が進まない方
- 高額な代償金を請求されて困っている方
- 相続財産に不動産が含まれており、評価に疑問がある方
- 自分でリフォームした家を守りたい方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】10年間放置された相続問題|負動産を回避し、代償金500万円を獲得したケース
【解決事例】10年間放置された相続問題|負動産を回避し、代償金500万円を獲得したケース
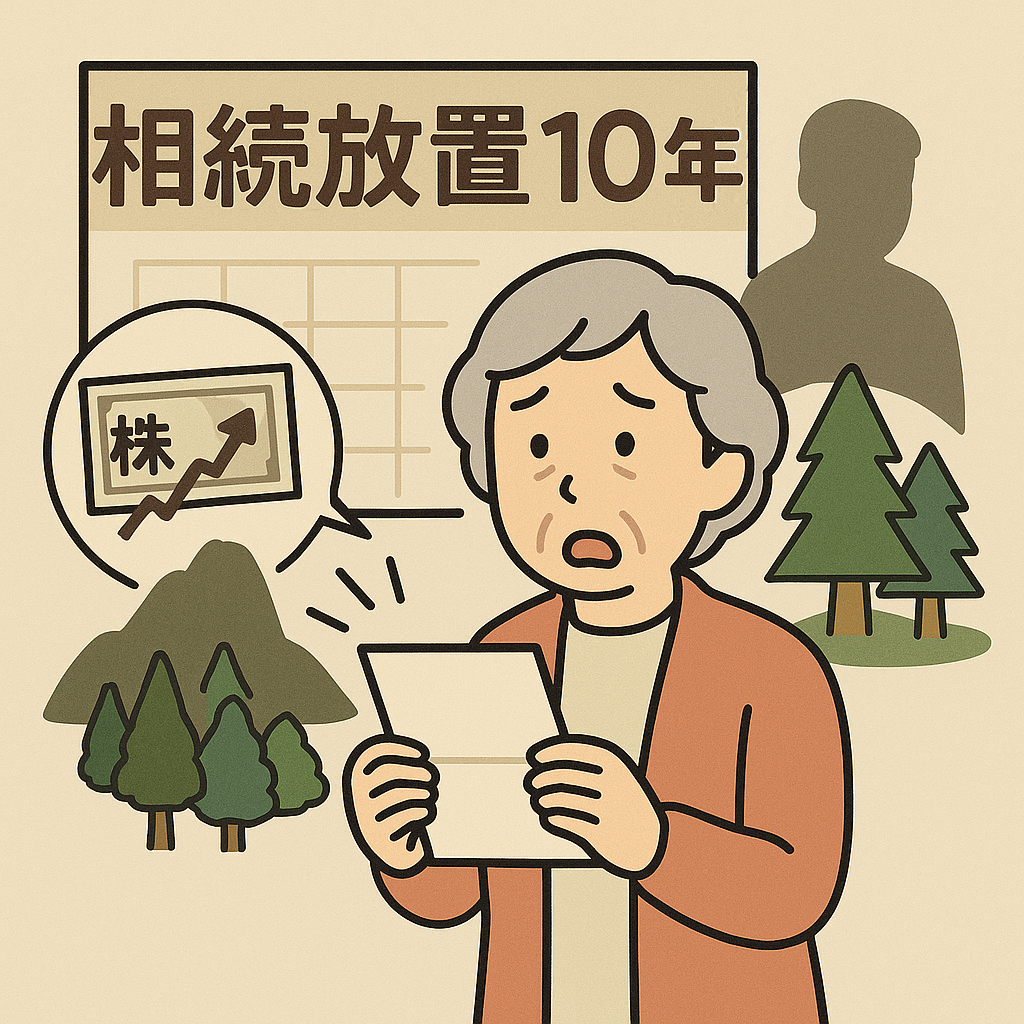
本件は、10年間放置されていた遺産分割において、株式の評価や代償金の支払いをめぐる交渉が行われた事例です。
弁護士が適切に遺産額を評価し、冷静に協議を進めたことで、スムーズな解決を実現し、依頼者にとって有利な条件で遺産分割が成立しました。
🔍 依頼者の状況
ご相談者:小林あやこさん(仮名)/70代女性
相続関係:被相続人(父)・兄妹間の相続
主な争点:遺産評価額・特別受益・負動産の扱い
小林あやこさんは、父・佐藤一郎さん(仮名)が10年前に亡くなった後も、兄妹間が疎遠だったことから相続手続を行わず、長年放置していました。
ところがある日、兄・佐藤忠さん(仮名)から「遺産をこちらで取得するので協力してほしい」との手紙が届きます。
突然の申し出に困惑したあやこさんは、「今さら何をどうすればいいのか分からない」と、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 遺産額を正しく評価
相手方から提示された遺産の内容は、不動産・預金・株式が含まれ、合計約400万円とのことでした。
しかし、株式については「父が亡くなった当時(10年前)の株価」で評価されており、現在の株価と大きく乖離していました。
また、負債として提示された内容には、葬儀費用・墓石代・行政書士報酬など、本来遺産に含まれるべきでない項目が多数ありました。
→株を時価額で評価すべきことなどを主張し、遺産総額は約1000万円相当であることを丁寧に説明・交渉しました。
② 兄の「会社承継」に特別受益の可能性
さらに調査を進める中で、兄が父の経営していた会社を無償で引き継いでいた可能性があることが判明しました。
これは、法的には「特別受益(生前贈与)」に該当する可能性があり、遺産分割の際には慎重に取り扱うべき重要事項です。
→ 会社の株式譲渡契約書や引継ぎに関する資料の開示を求め、交渉を継続しました。
③ 誰も欲しくない「負動産」の存在が明らかに
並行して、独自に調査を行った結果、被相続人の父名義ではない祖父名義の山林が多数存在していることが判明しました。
- 既に共有名義となっており、管理も困難
- 価値はほとんどなく、固定資産税だけがかかる負動産
- 誰が相続するかによって、将来の負担が大きく変わる
→ 当方では、この山林を兄が引き取ることを前提に、代償金額の調整を提案しました。
💡 解決結果|代償金として500万円を獲得
- 代償金として500万円の支払いを受けることで合意
- 不要な山林(負動産)を一切相続せずに済み、税・管理負担を回避
相続開始から10年が経過していたにもかかわらず、不利な条件をしっかり見直し、依頼者にとって有利な解決を実現することができました。
💬 弁護士からのアドバイス
「相続手続きが面倒で長年放置してしまった」「突然、遺産を譲ってほしいと手紙が来た」
そんなご相談は、当事務所にも数多く寄せられています。
相続は、時間が経過するほど遺産の内容が不明確になり、トラブルが起きやすくなる分野です。特に、以下の2点はとても重要です。
✅ 遺産を正しく評価すること
相続財産には、預金だけでなく、不動産や株式などが含まれます。
これらの価値を安易に計算すると、本来得られるはずだった相続分を大きく損なうことになります。
そのため、相続財産の内容や時価を正しく評価することが、適正な相続分を守るうえで極めて重要です。
✅ 特別受益(生前贈与など)を精査すること
たとえば、「兄が生前に父の会社を無償で引き継いでいた」などのケースでは、それが特別受益に該当する可能性があります。
これは法的に相続割合へ大きな影響を及ぼすため、契約書や取引記録などの有無をきちんと確認する必要があります。
📞 このような方は、ぜひご相談ください
- 相続を長期間放置している方
- 兄弟から突然「遺産を譲ってほしい」と言われた方
- 株や不動産の評価方法に納得がいかない方
- 相続したくない土地・山林がある方
- 代償金の金額に疑問を感じている方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。